Siena
| いくつかの美術館、教会を巡り、美術品を鑑賞するにしたがって、繰り返し描かれる主題がいくつかあることに気づく。そのいくつかは、聖書の中の話として思い当たるものもあったし、逆に背景を知らず興味もわかないものもあった。 シエナで出会ったその2点の絵画は強烈だった。同じ主題を扱った絵をフィレンツェでも目にしていたのだが、シエナでその作品を目にしたときは、しばらく絵の前を離れることができず、ただただ眺めていた。 |
ひとつは「嬰児大虐殺」。眼前の大殺戮の光景の中、狙われているのは赤ん坊ばかり。同じプッブリコ宮にある「善政のアレゴリー」「悪政のアレゴリー」よりもはるかに強く何かを訴えかけてきていた。それが、ヘロデ王の「嬰児大虐殺」をテーマにしたものだというのは、帰国後、美術書を調べてわかった。 |
| もうひとつは「聖セバスティアーノ」。3本の矢が体に刺さったその美しい青年は悲し気な目をして虚空を見上げている。他の街で出会ったどの聖セバスティアーノよりも、シエナの彼の目の悲しみは深いように思えてならなかった。彼のことを調べるためにやはり、帰国後に美術書を手繰った。 |  |
| いくつかの美術書の断片的な記述を拾ううちに、彼が殉教した聖人であることを知った。それと同時に彼が好んで描かれた理由も。当時ヴィーナスが女性の裸体像を描く口実とされたように、男性の裸体像を描くための口実とされたのが、聖セバスティアーノだったということを。 | 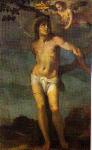 |
Copyright (c) 2000 Kimichi All Rights Reserved